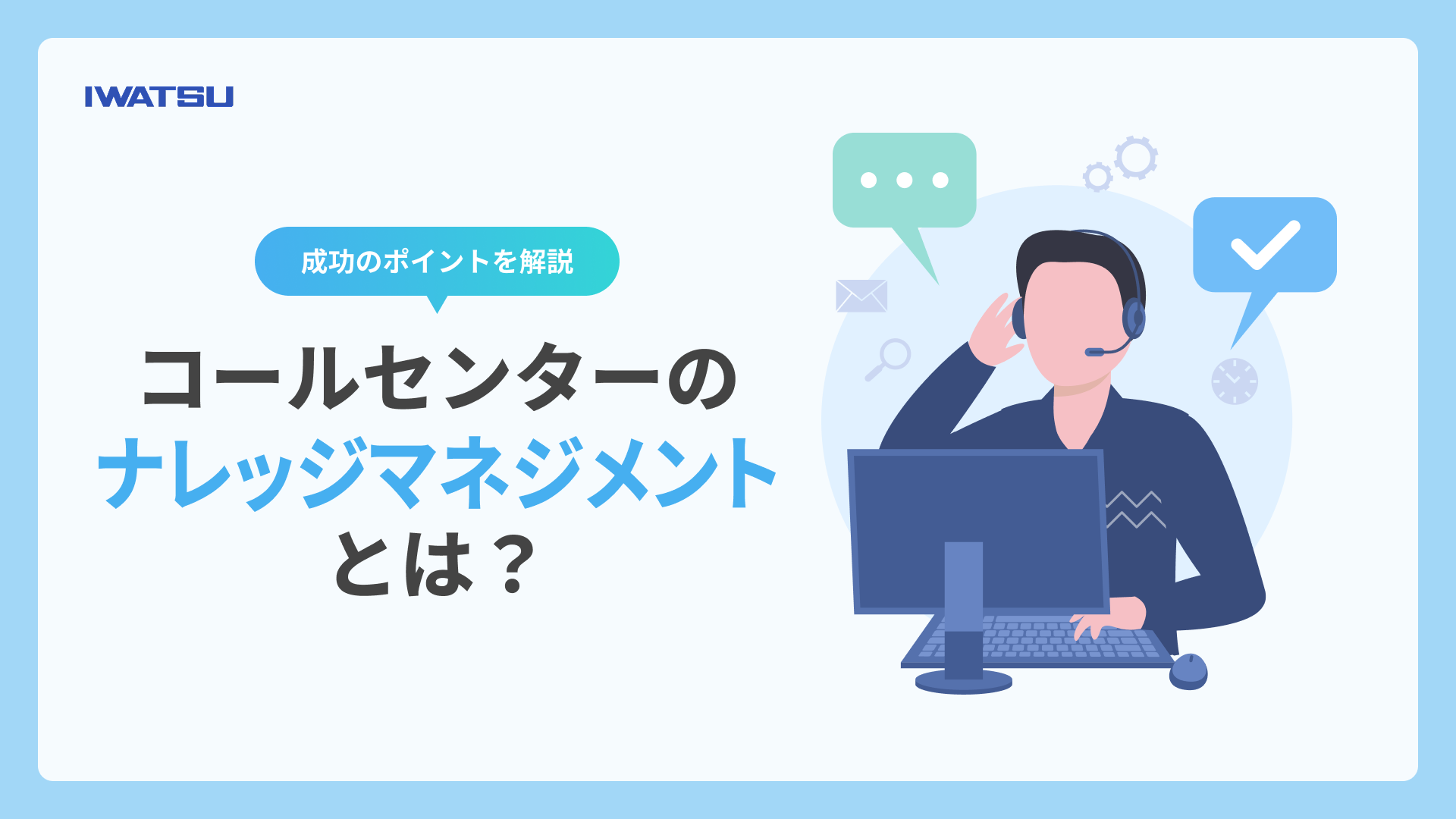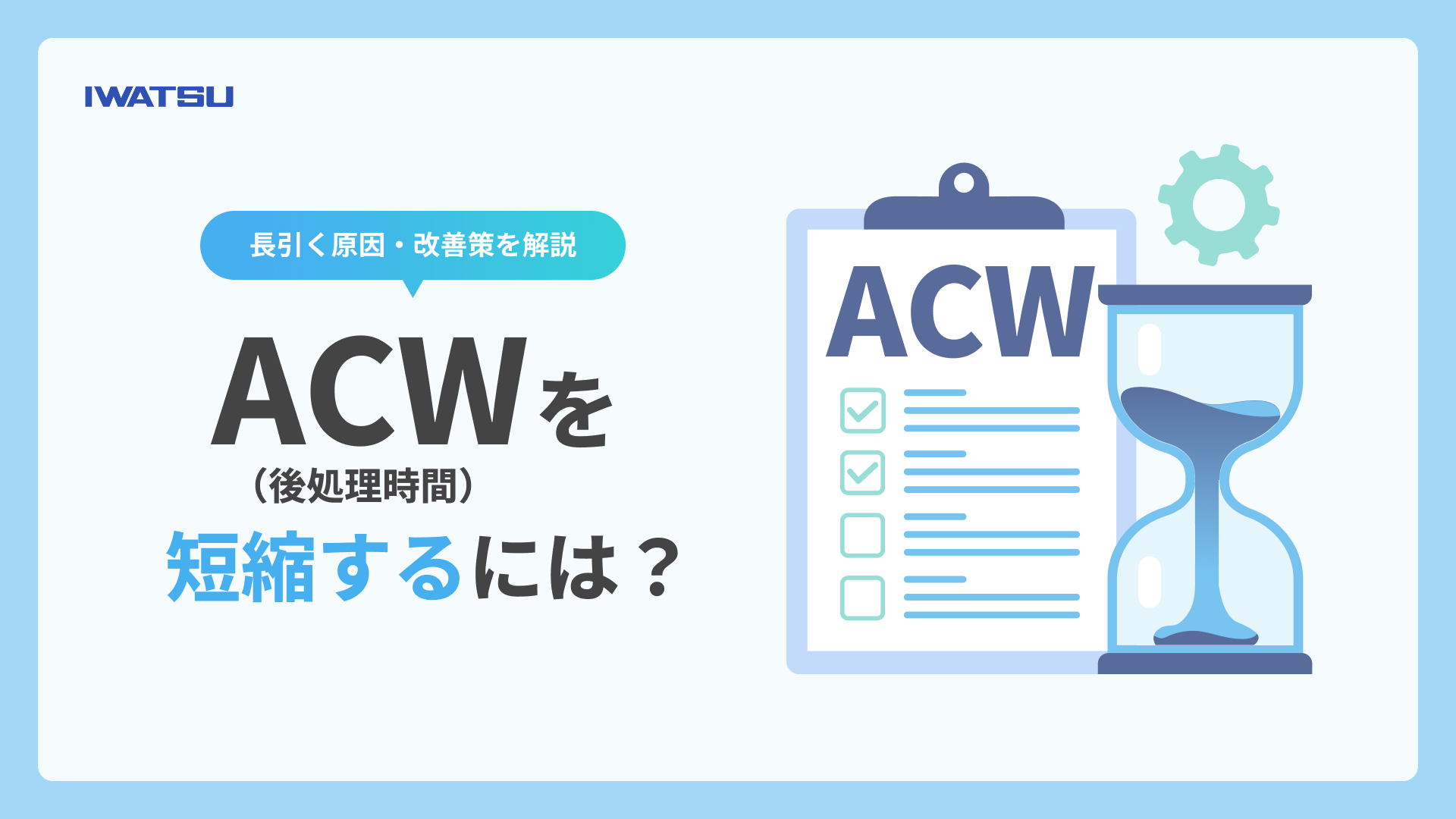knowledge

「オムニチャネル化」は、コンタクトセンターの理想像としてよく語られます。
電話・メール・チャット・SNSといった複数のチャネルをつなぎ、どの接点でも一貫した顧客体験(CX)を提供することが理想です。
しかし現場では、チャネルごとに別々のシステムを導入した結果、データが分断され、“マルチチャネル止まり”のケースが少なくありません。
理想と現実のギャップを埋めるためには、一気通貫の統合ではなく「段階的導入」がカギとなります。
本記事では、現場で実現可能なオムニチャネル化をテーマに、5つの導入ステップ、3つのシステム設計のポイントから、具体的な進め方を解説します。
オムニチャネル化はなぜ理想論で終わりやすいのか
オムニチャネル化は、理想的な顧客体験の提供を目指す一方で、実現は容易ではありません。背景には、チャネルの増加に伴う複雑化と、部分最適なシステム導入があります。
たとえば、チャット対応を急ぐあまり、既存のCRMとは連携しない形でツールを導入してしまう。メール・電話・チャット・FAQがそれぞれ独立した仕組みとなり、顧客情報がバラバラに管理される。
こうした状態では、オペレーターが過去のやり取りを把握できず、顧客は同じ説明を繰り返すことになります。
さらに、部門間の連携不足も大きな課題です。IT部門と運営部門が別々に判断し、全体の整合性を欠いた設計となることで、「システムはあるのに現場では使いにくい」「データはあるが活用できない」といった問題が生じがちです。
一括で統合を目指すと、現場負荷やコストが膨れ上がり、計画が途中で止まってしまうケースも少なくありません。これが、“理想論で終わる”構造的な理由です。
顧客体験が分断されるマルチチャネルの限界
「オムニチャネル化」とよく比較されるキーワードとして、「マルチチャネル化」があります。「マルチチャネル化」とは、複数のチャネルを並列に提供することを指します。
電話・メール・チャットといった接点を用意しても、データが連携していなければ、顧客は再び同じ説明を求められ、一貫性のない体験となってしまいます。
これは、顧客体験の分断だけでなく、運営効率の低下も招きます。チャネルごとにオペレーターが別のツールを開き、履歴を二重入力するなど、現場の負担も増大します。
一方、「オムニチャネル化」は、これらのチャネルを顧客単位で統合し、どの接点でも一貫した情報と応対を提供できる仕組みです。重要なのは「接点の数」ではなく、「体験の一貫性」。これを実現するには、戦略的な設計と段階的な実行が不可欠です。
現実的な解決策は“段階的な統合”
理想的なオムニチャネル化を一度に実現しようとすると、失敗リスクが高まります。現場が追いつかず、システムが使われないまま形骸化するケースも少なくありません。
成功のカギは、「全体構想 × 段階実行」。ゴールとなる顧客体験の全体像を描いた上で、優先度の高いチャネルから順に実装していくことが重要です。「理想を描きながら、現実的に実装する」姿勢こそ、現場定着の第一歩です。
オムニチャネル化を実現する5ステップ
ステップ1.現状分析:チャネル・システム・データの棚卸し
まずは、現在どのチャネルが存在し、どのシステムが使われ、どのデータが連携されていないかを把握します。オペレーターやSVへのヒアリングを通じて、二重入力や重複作業、更新漏れなど、現場の不便を洗い出します。
例:電話履歴がCRMに反映されていない、FAQが更新されずチャット回答とずれているなど。
ステップ2.理想像設計:顧客体験ゴールと全体構想
次に、目指すべき顧客体験の姿を定義します。「どのチャネルでも、過去のやり取りを踏まえて最適な対応ができる」「過去の問い合わせ内容を理解してAIボットが対応する」など、現場業務の理想シーンを描き、全体構想に落とし込みます。現場からのヒアリングを通じて、“こうなったら助かる”体験を具体化することが重要です。
ステップ3.優先チャネル選定:影響の大きいチャネルから着手
すべてのチャネルを同時に整備するのではなく、利用頻度が高く、改善効果の大きいチャネルから着手します。たとえば、全体の7割を占める電話問合せの効率化を図るため、まずはCRMとの連携・改善を第一ステップとして実施。成果を確認しながら、他チャネルへと拡張していきます。
ステップ4.共通基盤構築:CRM・FAQ中心のデータ統合
いきなり全システムをつなぐのではなく、現場が日常的に使うツールを中心に連携します。CRMやFAQなど、顧客対応のハブとなる基盤を整え、顧客IDをキーに電話やチャットなどの各チャネルの履歴を結びつけます。「よく使う」「すぐ役立つ」領域から統合を始めるのが成功のコツです。
ステップ5.段階展開と改善:PoC→パイロット→本格展開
まずは特定チームでPoC(小規模な実証)を実施し、応対時間短縮などの効果を定量化。効果が見えた段階で、社内共有を通じて合意形成を図り、パイロット(試験運用)→全社展開へ進めます。小さな成功の積み重ねが、大きな変革を生み出します。
オムニチャネル化を成功させるシステム設計 3つの重要ポイント
データ中心の設計思想:チャネルではなく顧客単位で考える
チャネルごとにシステムをつなぐのではなく、顧客を軸に設計することが重要です。顧客IDを中心に、すべての履歴・属性・ニーズを一元化することで、どのチャネルでも「同じお客様」として認識し、最適な対応が可能になります。
運用フローとの一体設計:現場が“使える”ことを前提に
どんなに高機能なシステムでも、現場で使われなければ意味がありません。設計段階から運用フローとセットで考え、現場の負担が減る仕組みにすることが成功の条件です。「操作がシンプル」「工数が減る」「情報が自動反映される」など、現場がメリットを実感できる設計が必須です。
ITと運営の協働体制:部門をまたいだ連携がカギ
IT部門だけでも、運営部門だけでも成功しません。要件定義から運用改善まで、両者が一緒に議論し、意思決定する体制を整えることで、齟齬や手戻りを防ぎ、スムーズな導入が可能になります。「システム」と「現場」が同じ方向を向くことが、定着のカギです。
岩崎通信機が支援できること
岩崎通信機は、コンタクトセンター領域に特化したシステムの構築会社として、オムニチャネル化の構想策定から設計・構築・保守までを一貫して支援します。現場で実際に活用され、長期的に運用が続くことを前提とした、“使われるシステム”の実装が強みです。
- 段階的導入の設計支援
現状分析から全体構想の整理、優先チャネルの明確化
- システム設計・構築支援
CRM・PBX・チャット・FAQ・AIボットなど、既存システムとの柔軟な連携構築
- PoC・試験運用サポート
小規模導入で効果を検証し、改善提案を通じて定着を支援
- 保守・サポート体制:
運用開始後も安全・安定的に稼働できるよう、継続的な技術サポートを提供
特に、PBXとCRMの連携設計、データ連携基盤の構築など、実際の現場で“使われる”ことを前提とした構築に強みを持っています。
岩崎通信機では、単なるシステムの構築ではなく、「現場で活きる仕組みを共に作る技術パートナー」として、オムニチャネル化の構想から安定運用までを一貫して伴走します。
▶︎ 詳細はこちら
まとめ
オムニチャネル化は、一度に完成させるプロジェクトではなく、段階的に育てるプロセスです。「全体構想を描きながら、小さな成功を積み上げる」ことで、理想は現実になります。
データ中心設計、運用一体化、部門協働――この3つを揃えることで、現場に定着し、顧客体験を変える仕組みを実現できるのです。
岩崎通信機は、構想から設計・構築・保守までを一貫して支援し、現場で活用されるオムニチャネル化の成功に向けてご支援します。
この記事を書いた人
藤井直樹
コールセンター業界で20年以上SEとして従事。
アナログ時代から今に至るまで現場に近い場所で技術の移り変わりを経験。
公共、金融業界、BPO業界の経験が豊富。